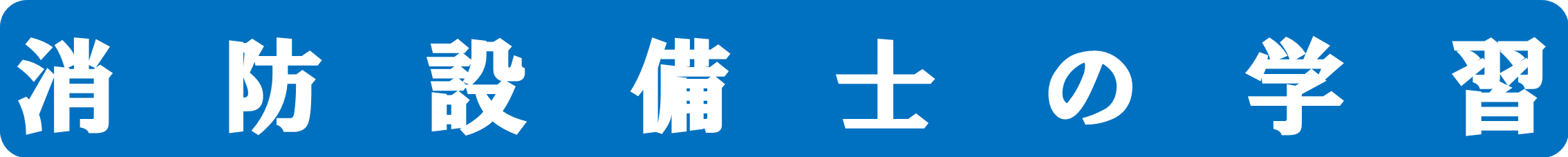自衛消防組織ってなに?3分でわかるシリーズ、設置する必要のある建物、業務、統括管理者、講習、要員の数、根拠法令
自衛消防組織とは、災害発生時の応急対策を円滑に行う体制を整備することを目的とした組織であり、多数の人が出入りする大規模・高層の建物で設置することが義務付けられています。
設置義務のある建物規模
法8条で防火管理者を選任する必要がある建物であり、以下に該当する規模であること。
①施行令別表第一(1~4,5イ,6~12,13イ,15~17項)のうち次のいずれかに該当するもの
・地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上
・地階を除く階数が5以上の防火対象物で、延べ面積2万平方メートル以上
・地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上
②施行令別表第一(16項の用途で①の用途が含まれているもの)のうち次のいずれかに該当するもの
・地階を除く階数が11以上の建物のうち
・①の用途の全部又は一部が11階以上にあり、その部分の合計が1万平方メートル以上
・①の用途の全部が10階以下にあり、かつその部分の全部又は一部が5階以上10階以下にあるもので、その部分の合計が2万平方メートル以上
・①の用途の全部が4階以下にあり、その部分の合計が5万平方メートル以上
・地階を除く階数が5以上10以下の建物のうち
・①の用途の全部又は一部が5階以上にあり、その部分の合計が2万平方メートル以上
・①の用途の全部が4階以下にあり、その部分の合計が5万平方メートル以上
・地階を除く階数が4以下の建物で、①の用途の部分の合計が5万平方メートル以上
③施行令別表第一(16の2)の建物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
自衛消防組織の業務と編成
自衛消防組織の業務は、一定の設備・資機材等を備え、火災等の発生時において、消防計画に定められた事務分担により、初期消火、消防機関への通報、在館者の避難誘導等、火災等による被害を軽減するために必要な業務を行うこととされています。
そのため、基本的に以下の図のような体制を取り、安全に備えています。
編成の一例

統括管理者ってなに?
統括管理者は、指揮命令系統を明確にする事により、従事する要員の安全確保を行いつつ、初期消火等の業務についても迅速・的確に行うために配置されている人です。
また、統括管理者は誰でもなれるわけではなく、自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した人や統括管理者として学識経験を有すると認められた人に限られています。
自衛消防活動中核要員の算定について
自衛消防活動中核要員制度は、昭和47年に創設されましたが、その後複数回にわたり制度の強化等が行われてきました。さらに、平成31年3月12日付けで「火災予防条例施行規則及び火災施行規則の一部改正並びに自衛消防活動中核要員制度に係る運用及び指導について」の改正規則及び改正告示が公布されたことにより、自衛消防活動中核要員の人数の算定が変更されました。
根拠法令について
自衛消防組織については、消防法第8条の2の5で定められており、自衛消防活動中核要員は、火災予防条例第55条の5(東京都の場合)で規定されています。
まとめ
今回は、自衛消防組織及び自衛消防活動中核要員について説明しました。大規模な建物や企業に努めることになると、実際に自衛消防組織の一員になることがあります。その時に自衛消防組織がどうゆうものなのかを知っているだけでも適切な活動が出来ると思います。また、統括管理者になる方は簡単に説明等が出来るぐらいには知識として持っていて頂きたいです!
よく読まれている記事一覧
» 防火管理者ってなに?1分でわかるシリーズ、防火管理講習、防災管理者との違い、根拠法令
» 収容人員ってなに?1分でわかるシリーズ、なぜ必要なのか、把握しておかないとヤバイ?、計算方法、根拠法令
» 防災管理者ってなに?1分でわかるシリーズ、防災管理講習、防災管理者が必要な建物、業務の大変さ、根拠法令
» 統括防火管理者ってなに?1分でわかるシリーズ、防火管理講習、防災管理者との違い、根拠法令
» 自衛消防組織ってなに?3分でわかるシリーズ、設置する必要のある建物、業務、統括管理者、講習、要員の数、根拠法
カテゴリー一覧
» 消防法の解説
» 消防用語集
» 消防設備士の学習
» 全国の消防組織
» 消防の予防を学ぶ
» 防災を学ぶ
» 建築と消防